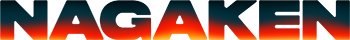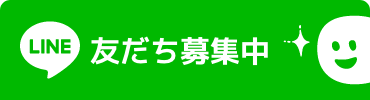忙しい毎日でも、部屋をスッキリ片づけるコツさえつかめば快適な暮らしは手に入ります。小さなことから始めれば、片づけは決して難しくありません。子どもが散らかしがちな家庭でも無理なく続けられる工夫や、散らからない仕組みづくりのポイントも紹介。
本記事では、初心者でも簡単に実践できる片づけ方法を、基本のルールから具体的なステップ、収納アイデアまで徹底解説します。
ストレスを減らし、心にゆとりを生む片づけ術をぜひ試してみましょう。
<こちらも参考|家事代行で片付け・整理整頓!忙しいあなたに贈る時短テクニック>
もくじ
片づけの基本ルール

片づけを成功させるために、まず押さえておきたい基本のルールがあります。「出す・分ける・収納する」という3つの手順が片づけの基本です。具体的には、全ての物を一度出して現状を把握し、「必要な物」と「不要な物」に分け、最後に定位置を決めて収納する流れです。
このとき、「いる/いらない」の判断に迷う物は一時保管し期限を決めて見直すルールを設けましょう。また、一度に家全体を片づけようとせずエリアを決めて少しずつ進めることも大切です。片づけが苦手な人ほど最初に欲張りがちですが、狭い場所から始めて達成感を積み重ねる方が効果的です。
さらに、使った物は必ず元の場所に戻す習慣づけも重要です。物の「住所」を決め、使い終わったらそこに戻すことを徹底すれば散らかりにくくなります。これら基本ルールを意識するだけで、片づけの効率と維持力が格段にアップします。
片づけに必要な道具

片づけを始める前に、事前に必要な道具を準備しておきましょう。最低限揃えておきたいのは以下のものです。
- ゴミ袋: 不要な物やゴミをどんどん入れていけるよう、大きめサイズ(45Lなど)のゴミ袋を用意します。燃えるゴミ・燃えないゴミ・資源ゴミ用など、地域の分別ルールに合わせ複数種類あると便利です。片づけ中に出たゴミはその都度袋に入れ、床に仮置きしないようにしましょう。
- ビニール紐とハサミ: 古新聞や雑誌、ダンボールなど束ねる際に使います。不要な本類を縛ってまとめておけば持ち運びやすく、片づけ途中にうっかり蹴散らしてしまう心配も減ります。
- 段ボール箱: 整理用に「必要」「不要」「保留」の3つの箱を用意しましょう。片づけ対象の荷物を一時的に分類収納するのに便利です。「必要」な物は後で収納し、「不要」な物は処分へ。判断に迷う物は「保留」箱に入れ、一定期間後に改めて要不要を検討します。段ボールはスーパーや家電店でも無料でもらえる場合があります。
上記に加え、必要に応じてマスクや手袋(ホコリ対策)、マジックペン(箱に中身や期限を書く用)なども用意すると作業がスムーズです。
簡単に始められる片づけのステップ

どんな部屋でも共通する「出す→分ける→しまう」の3ステップを順番に実践すれば、効率よく確実に片づけられます。
ここでは初心者でも取り組みやすい、基本的な片づけの進め方を3つのステップで紹介します。
ステップ1:収納から全部出す
まずは収納場所にある物をすべて取り出します。一度全部出すことで、家に何がどれだけあるか把握できるからです。収納にしまったままでは、持ち物の量や種類を正確に掴みにくいもの。
広めのスペース(床やテーブルの上など)を確保して、一箇所ずつ取り出していきましょう。例えばクローゼットなら中の衣類や箱を一旦すべて外に出します。
ただ、一度に家中の物を出す必要はありません。「今日はこの引き出し」といったようにエリアを区切り、順番に進めるのがコツです。
全部出し終えたら、どれだけの物があったか一目で確認できます。「こんなに持っていたんだ」と実感することで不要な物を減らす意識も高まります。また、一時的に収納が空になるので掃除もしやすくなり、ホコリだらけだった棚を拭くチャンスにもなります。
ステップ2:「使う物」と「使わない物」に分ける
取り出した物を仕分け(分類)します。ここでのポイントは、「使える/使えない」ではなく「使う/使わない」で判断することです。「いつか使えるかも」と思って残していては、物は永久に減りません。この1年間で一度も使わなかった物は、今後も使う可能性が極めて低いと考えましょう。
まずは、よく使う物・たまにしか使わない物・不要な物の3種類にざっくり分類します。例えば衣類なら「日常的によく着る」「年に数回程度」「全く着ない」に分けるイメージです。同時に、物の種類ごとにグループ分けしておくと、この後の収納作業が楽になります。
迷う物があれば無理に今決めなくても構いません。先述の「保留ボックス」に入れて次のステップへ進みましょう。仕分けを後回しにした物は、片づけ作業の最後に再度見直します。特に思い出の品や家族の持ち物は処分に悩みがちなので、後回しにして一通り片づけてから判断するとスムーズです。
ステップ3:使う物を収納する
仕分けが終わったら、残すと決めた「必要な物」だけを改めて収納します。ここでも収納のコツを意識しましょう。
まず、使用頻度に応じて収納場所を決めます。よく使う物はすぐ手に取れる取り出しやすい場所に、あまり使わない物は奥や高い所に収納すると便利です。例えば日常的に使うリモコンはリビングの手の届く所に置き、めったに読まない本は本棚の上段に、といった具合です。
カテゴリーごとに収納場所をまとめるのも探し物防止に有効です。例えば文房具類は引き出し一段にまとめる、季節家電は一つの棚に集める、など種類別に定位置を決めましょう。
さらに、収納する際は詰め込みすぎないことも大切です。収納スペースには7~8割程度の余裕を残すと出し入れしやすく、新しい物も受け入れやすくなります。
最後に、「不要」と判断した物はゴミに出すかリサイクルへ回します。ここまでで片づけ作業は完了です。スッキリ片づいた空間を維持するため、使った物は必ず元の場所に戻す習慣を心がけましょう。
断捨離のすすめ

「断捨離」とは不要な物を断ち、捨て、物への執着から離れる考え方です。片づけを進める上で、この断捨離マインドを取り入れると効果的にスッキリできます。
まず、「ここ1年使わなかった物」は思い切って手放すのが基本です。「いつか使うかも」と取っておいても使わない可能性が高く、場所を圧迫するだけと心得ましょう。
次に“もったいない”と捨てられない物への対処です。「まだ使えるのに…」と感じる場合は、リサイクルショップやフリマアプリに出すのも一つの方法。他の必要な人に使ってもらえば罪悪感も薄れ、自分にとって不要な物を減らせます。
「保留ボックス」を活用するのもおすすめです。迷う物はいったん保留ボックスに入れ、○ヶ月後に再チェックしてそれでも使っていなければ処分する、といったルールを設けます。こうすることで悩んで先に進まない事態を防ぎつつ、時間をおいて客観的に要不要を判断できます。
断捨離を習慣づけると、物が増えすぎず片づけ自体が楽になるという大きなメリットがあります。クローゼットや押入れも自然とスペースに余裕が生まれ、掃除や収納の手間も減るでしょう。ぜひ「新しく物を迎えるために古い物を手放す」意識で断捨離を進めてみてください。
カテゴリー別の片づけ方法5選

散らかりやすい物はカテゴリーごとに片づけ方のコツがあります。ここでは衣類、書類、子どものおもちゃ、キッチン、リビングの5つに分けて、それぞれ効果的な整理整頓の方法を紹介します。
一つひとつのカテゴリーに合った片づけ術を取り入れることで、家じゅうを効率よくキレイに保てます。
1. 衣類の片づけ方法
衣類は量が多くなりがちで、定期的な見直しが必要なカテゴリーです。まずクローゼットやタンスからすべての服を一度出して「着る服」と「着ない服」に分けることから始めましょう。
ポイントは「ここ1年着なかった服」は思い切って処分候補にすること。迷う服は先述の保留ボックスに入れて、決めた期限まで着なければ手放す判断を。仕分け後、残す服はシーズンごとや種類ごとに分類して収納します。ハンガーに掛けられるものは積極的に掛けましょう。
特によく着る普段着は畳むより吊るす収納にした方が取り出し・片づけの手間が少なくなります。ハンガーパイプいっぱいに掛ける場合でも、7割程度の密度に収めておくと服が探しやすくシワにもなりにくいです。
引き出し収納する衣類は立てて収納すると一目で見渡せます。衣替えの際に不要になった服を処分する習慣をつければ、クローゼットの容量オーバーも防げます。
さらに、家族それぞれの衣類は人別に収納場所を分けると散らからず管理しやすくなります。
2. 書類・紙類の片づけ方法
書類や紙類は放置するとどんどん増えるため、こまめな整理が大切です。基本は「その場ですぐ仕分け・処分」を徹底しましょう。例えば郵便物や学校からのプリント類は、要・不要を即座に判断して不要なものはすぐ捨てるのが鉄則です。レシートやDM、チラシなども「とりあえず取っておく」を極力やめ、必要なものだけ残す習慣をつけます。
とはいえ、忙しいと難しい場合もあります。その場合は「一時ボックス」を活用しましょう。帰宅後すぐ確認できない郵便物や、後で処理したい紙類はひとまず専用のカゴやボックスに入れておきます。このボックスは中が見えないおしゃれな箱をリビングに置いても良いでしょう。
ポイントは定期的に中身をチェックして空にすることです。例えば週末にボックス内の書類を整理し、要るものはファイルへ、不要なものは処分すると決めておけば紙類が散乱しっぱなしになるのを防げます。重要書類はカテゴリー別のファイル(例:医療、保険、学校関係など)にまとめて、すぐ取り出せる場所に立てて収納します。
紙類は溜め込まないことが何よりのコツです。
3. 子どものおもちゃ・学用品の片づけ方法
子どものおもちゃや学用品はリビングや子ども部屋に散乱しがちな代表格です。まずおもちゃの数を適切に管理するために、壊れていたり遊ばなくなったものは定期的に整理しましょう。子どもと一緒に「もう使わないおもちゃ」を選んで処分したり、増えすぎたら新しい物と入れ替えるルールを作るのも効果的です。
収納面では細かく分類しすぎないことがポイント。大きさや種類がバラバラなおもちゃ類は、細分類すると子ども自身が片づけづらくなります。そこで、大まかなカテゴリーで“ざっくり収納”を心がけましょう。例えばブロックや積み木は一つの大箱にまとめて放り込む、人形やフィギュアもざっくり一緒のカゴに入れる、といった具合です。
お片づけしやすい収納グッズを使うのもコツです。子どもでも出し入れできる軽い素材のカゴや引き出し式収納がおすすめです。例えばIKEAの「トロファスト」のようなフレーム+収納ボックスは、ボックスごと子どもの近くに持っていけて散らばったおもちゃをザザッと入れられるので、子どもでも片づけが完了しやすい仕組みです。
また、収納ボックスに写真やイラストのラベルを貼って中身を示すと、小さい子でも遊び終わりにどこに片づければ良いか分かりやすくなります。子どもの成長に合わせて収納方法も見直し、片づけの習慣を身につけさせましょう。
4. キッチンの片づけ方法
キッチンは物が多く、ごちゃつきやすい場所の一つです。まずはシンク下や戸棚の中など収納スペースごとに中身を全部出し、不要な調理器具や賞味期限切れの食品がないか確認・処分します。一度出したら種類別にまとめてから収納し直しましょう。
使用頻度の高い物は取り出しやすい場所に収納するのが鉄則です。例えば、毎日使う調味料や鍋・フライパンはコンロ周りの手が届く位置にまとめて配置します。お玉やフライ返しなども吊り下げておけばサッと使えて便利です。逆に、滅多に使わないホットプレートや来客用食器などはシンク下の奥や吊戸棚の上段にしまってOK。こうすることで日常使いの物がすぐ取り出せて片づけもスムーズになります。
また、キッチンではデッドスペースの活用も大切です。例えばシンク下の扉裏にフックを付けて鍋ぶたやラップを掛ける、冷蔵庫の上に突っ張り棚を設置して空間を収納に変える等です。キッチン背面のカウンター上部にラックを置けば上方のデッドスペースに物を置けるようになり、家電や食品の置き場を追加できます。
収納容器も活用しましょう。調味料や乾物は中身が見える保存容器に移し替えて統一すると在庫管理しやすく見た目もスッキリします。動線も意識し、調理中によく動く範囲(シンク~コンロ周り)には必要な物だけを置くようにすると、ごちゃつかないキッチンが維持できます。
5. リビングの片づけ方法
リビングは家族全員が使う空間だけに物も集まりやすい場所です。まずテーブルやカウンターの上に物を置かないことをルールにしましょう。ダイニングテーブルなどはつい郵便物や雑誌の仮置き場になりがちですが、「ここには物を置かない」と決めるだけでかなりスッキリします。
リビングで散らかりがちな物は収納場所を予め決めておくことが大切です。例えば散乱しやすいリモコン類はリモコンラックやかごを用意して定位置へ。家族それぞれの持ち物も、リビングに持ち込むことが多いなら人別の収納ボックス(例えばママ用、子ども用のカゴなど)を設けると良いでしょう。共有で使う文房具や薬などはリビングボードの一角にまとめ、誰でも取り出せて使ったら戻すしくみを作ります。
学用品をリビングで使う場合は、専用の棚やワゴンを用意してそこに片づける習慣をつけると散らかりません。また、見た目を整える工夫として収納用品を統一する方法があります。リビングに置く収納ボックスは色やサイズを揃え、中身が見えないタイプを使えば生活感が出ずスッキリします。中に何が入っているかわかるようラベリングもしておくと、家族みんなが元の場所に戻しやすくなります。
リビングは「出したらすぐ戻す」を家族全員で徹底し、物が出しっぱなしにならない仕組みを作ることが最大のコツです。
収納方法のアイデアとテクニック5選

続いて、部屋を散らかりにくくする収納のアイデアを5つ紹介します。収納のテクニックを駆使すれば、今あるスペースを有効に使って物をスッキリ納めることが可能です。
ちょっとした工夫で収納力がアップし、“見せる収納・隠す収納”のメリハリもつけられます。ぜひ取り入れてみましょう。
アイデア1:収納は7~8割の余裕を持たせる
収納棚や引き出しに物を詰め込み過ぎないことは収納の基本テクニックです。隙間なくビッシリ収納すると一見キレイに見えますが、取り出しにくく新しい物の入る余地もなくなってしまいます。
収納スペースには容量の7~8割程度にとどめるのが使いやすさのコツ。余白があると物の出し入れがスムーズですし、急な来客時にとりあえず物をしまうスペースとしても活用できます。
また、スペースに余裕があれば空気の通り道ができてカビ防止にもなります。収納容器や衣装ケースもパンパンに入れず、2割は空きをキープする習慣をつけましょう。余裕を持たせることで見た目にもゆとりが生まれ、ゴチャゴチャ感が軽減します。
アイデア2:ものは立てて収納する
収納のポイントは「とにかく立てる」こと。衣類・書類・小物類、なんでも可能な限り縦置きに収納すると一目で中身が分かり、使いたいものをサッと取り出せます。
重ね置きしてしまうと、下のものが見えなくなったり重みで潰れてしまったりします。下の物を探すために上の物をどかす手間が生じ、出し入れが面倒になる原因です。
例えば引き出しの中の衣類は丸めて立てて収納、書類はブックエンドで仕切って立てる、バッグ類も仕切り板を使って立てて並べる、といった具合です。収納ケース内でもファイルボックスなどを活用して中身を立てて分類すると良いでしょう。100円ショップの仕切りスタンドや書類ケースは、引き出し内で物を立てるのに役立ちます。
物を立てて収納する習慣をつければ、「どこに何があるか」一目瞭然。探し物による時間ロスも減らせます。
アイデア3:見えない収納ボックスで統一感を出す
収納棚やオープンラックには中身が見えない収納ボックスを使うと、見た目がスッキリまとまります。中身を隠せるボックスなら、中が多少ごちゃついていても部屋全体の印象を損ねません。
特にカラーボックスや棚に複数のボックスを並べる場合、サイズやデザインを揃えると統一感が出ます。例えば同じ色・形のボックスを使えば、それだけでスッキリ整った印象になります。おもちゃ収納などでもカラフルな中身を白やグレーのボックスで隠せば、リビングの雰囲気に馴染みやすくなるでしょう。
注意点は「入れっぱなしにしない」こと。ボックスに放り込むだけの収納は楽ですが、中で散らかったまま放置すると結局何がどこにあるか分からなくなります。そこでラベルを貼るなどして中身を識別できるようにしましょう(次項参照)。ボックス収納+隠す+ラベリングで、見た目と機能性を両立した収納を目指せます。
アイデア4:ラベリングで誰でも分かる収納に
ラベルを活用して、物の定位置を誰にでも分かるよう表示しましょう。ラベリングは中身を示す「収納の表札」のようなものです。貼っておくだけで戻すべき場所がひと目で分かり、出し入れがしやすくなる効果があります。
特に家族がいる場合、ラベルがあれば「○○はどこ?」と探し物に困る場所でも自分で片づけてもらいやすくなります。ラベルはテプラなどのラベルライターで作成しても良いですし、マスキングテープに手書きして貼るだけでもOKです。お子さんには文字より写真やイラストのラベルが効果的です。例えばおもちゃ箱におもちゃの写真を貼れば、小さな子でもどこに片づければいいか理解できます。季節物の収納ケースにも内容物をラベリングしておけば、衣替え時などに探す手間が省けます。
さらに、ラベリングされた収納は元の場所に戻す意識を高めてくれる効果も指摘されています。片づけた場所が散らかりにくくなり、片づけ時間の短縮にもつながるという報告もあります。ぜひ収納ボックスやファイル、棚板などにラベルを貼って「誰が見ても分かる収納」を目指しましょう。
アイデア5:突っ張り棚やフックでデッドスペースを活用
見落としがちなすき間空間(デッドスペース)を収納に変えるテクニックです。例えば家具と天井の間や棚の上部など、活用されていない隙間に突っ張り棚を設置すれば、新たな収納棚として使えます。
実際にキッチン背面のカウンター上にラックを置いて、その上段にパンケースやカゴを収納している例があります。家電を横にずらりと並べるよりも上方を使うことで、同じ物量でも見た目がすっきりする効果があります。
また、壁面や扉裏もデッドスペースになりがちです。ここにはフックやウォールラックを取り付けて有効活用しましょう。玄関扉の裏にフックを貼り付けて帽子掛けに、キッチンシンク下の扉裏にラックを吊るしてまな板やラップの収納に、といった具合です。壁に穴を開けられない賃貸でも、粘着フックやマグネット式のフック・ラックが市販されています。これらを活用すれば工具不要で簡単に収納スペースを追加できます。
さらに、家具のちょっとした隙間にもスリムワゴンや隙間収納ラックを差し込めば、飲料のストックや掃除用具入れに早変わりです。家の中の未活用スペースを探してみて、収納拡張に役立ててください。
片づけを習慣化する方法

片づけは一時的に頑張るだけでなく、日々の習慣にしてしまうと散らかりにくい家をキープできます。
ここでは、忙しい人でも続けられる片づけ習慣のコツを紹介します。無理なく生活の中に片づけを組み込み、家族みんなでスッキリ空間を維持しましょう。
方法1:片づけの時間・曜日を決める
まず片づけをする時間や曜日をあらかじめ決めておくことが効果的です。人は予定に組み込まれていると自然と行動に移しやすくなるもの。例えば「平日は夜10分間だけ片づけタイムを作る」「毎週金曜日の夜はリビングの整理をする」といった具体的な片づけルーティンを設定しましょう。
曜日ごとに片付ける場所を決めてしまうのもおすすめです。「月曜はキッチン」「火曜は玄関」など習慣化すれば、家全体をまんべんなくリセットできます。時間を決めてタイマーをセットして行うのも良い方法です。「19時までに終わらせる」と決めると逆算してテキパキ動けますし、時間を区切らないとダラダラ長引いてしまうのを防げます。週1回でも習慣にできれば上出来ですが、難しければ月1のプチ断捨離デーを設けるなど自分に合う頻度でOKです。
いずれにせよ「何もしない日が続く」状態を避け、定期的にリセットする習慣を持つことが片づけ維持の近道です。
方法2:「ながら片づけ」でスキマ時間を活用
忙しくてまとまった時間が取れない人は、別の作業と同時進行で片づける工夫をしてみましょう。いわゆる「○○しながら片づけ」です。例えば歯磨きしながら洗面台周りを整える、服を着替えながらクローゼット内を整理するなど、日常動作の合間に少し片づけを加えます。
小さな時間の積み重ねでも侮れません。テレビのCM中にリモコンや雑誌を定位置に戻す、炊飯中にキッチンカウンターを片づける、といったスキマ時間の片づけも効果的です。
「ながら片づけ」の利点は、特別に片づけの時間を確保しなくても部屋が整っていくことです。忙しいママ・パパには特におすすめの方法で、育児や仕事の合間に少しずつ家が片づいていけばストレスも軽減します。
ポイントは毎日の習慣に紐付けること。歯磨き=洗面所リセット、帰宅直後=バッグの中身を所定位置へ戻す、のように決めておくと自然に体が動きます。無理なくスキマ時間を活かして、気づけば「いつもキレイ」を実現しましょう。
方法3:音楽やご褒美を取り入れて楽しく継続
片づけを苦痛な作業ではなく楽しい時間に変える工夫も大切です。一番簡単なのは音楽をかけること。お気に入りの曲やノリノリになれる明るい音楽をBGMに流せば、気分良く体が動きます。無音で黙々とやるよりストレスが溜まりにくく、「あともう少し頑張ろう」とやる気も続きます。
家族で片づけるときは音楽をかけて“ミュージカルお掃除”風にするのも盛り上がります。加えて、自分へのご褒美も用意しましょう。「片づけが終わったらお気に入りのスイーツを食べる」「夜ゆっくり映画を見る」など、作業後の楽しみを設定するとモチベーションが上がります。
このご褒美作戦は子どものお片づけ教育にも効果抜群です。おもちゃの片づけができたらシールを貼って褒める、全部片づいたら一緒にゲームで遊ぶ時間を作る、など達成感を味わわせる工夫を。楽しみややりがいを感じられれば、片づけは辛い家事ではなく前向きに取り組める習慣になります。
方法4:家族でルールを決めて協力する
家族と暮らしている場合、家族全員で片づけのルールを共有し、協力して維持することが重要です。一人が頑張って片づけても他の家族が散らかし放題では意味がありません。
まず物の定位置(住所)を決めてラベルなどで明示し、誰でも片づけられるようにします。例えばハサミは引き出し中央のトレー、ランドセルはリビング入口のフック、といった具合に置き場所をはっきり決めて宣言しましょう。
大切なのは、使った人が元の場所に戻すという当たり前のことを家族全員が実行することです。「出したら戻す」を習慣づければ、散らかってもすぐリセットできます。親が実践し、子どもには根気強く教えましょう。ゲーム感覚で「おもちゃ10個しまえるかな?」と競争したり、片付け当番をローテーションするのも手です。
さらに「新しいおもちゃを買ったら古いものを一つ手放す」など家族のルールを作ると、物の増えすぎを防ぎやすくなります。家族で声を掛け合い協力すれば、負担も一人に偏らず散らかりにくい快適空間が維持できます。
片づけ後の維持管理のポイント

せっかくキレイになった部屋も、油断するとすぐ元通り…ということになりかねません。最後に、片づけ後のキレイな状態を維持するためのコツを紹介します。
物を増やさない工夫や定期的なチェックなど、ちょっとした心がけで“散らからない部屋”をキープしましょう。
ポイント1:物を増やしすぎない工夫をする
物の総量をこれ以上増やさないことが、散らかり防止の基本です。具体的には新しい物を買う際は本当に必要か吟味するクセをつけましょう。似たような物を持っていないか確認し、代用できる物がないか考えてみます。
どうしても購入するなら、「ひとつ買ったらひとつ捨てる」を徹底します。また、日用品の買い置きをしすぎないことも大事です。例えば特売だからとトイレットペーパーを大量に買い込むと置き場所に困り、部屋が雑然としがちです。収納スペースに余裕がない場合は、必要最低限のストック量に留めましょう。
こうした意識で物の出入りをコントロールすれば、勝手に物が増えて収納オーバー…という事態を防げます。日頃から「本当に今これが必要か?」「家のどこに収められるか?」と自問する習慣を持つことが大切です。
ポイント2:定期的に片づけ&見直しをする
定期的に部屋をリセットする機会を設けましょう。片づけた直後はキレイでも、生活していれば多少物は動きます。理想は「出しっぱなしの物がない状態」を継続すること。そのために、例えば、毎晩寝る前5分の片付けを日課にすると良いです。難しければ週1回のプチ片づけデーでも構いません。
さらに、季節の変わり目や長期休暇に大掃除を兼ねて整理整頓すると効果的です。「いつの間にか増えた不要品」が出てきたら処分し、収納方法も必要に応じてアップデートします。
収納がパンパンで入りきらなくなってきたら要注意。物が収納しきれず床や棚の上に置くようになったら、自分が管理できる量を超えているサインです。その場合は思い切って不要物を減らすか、収納方法を見直すタイミングと捉えましょう。
一定のサイクルで片づけと点検を行えば、リバウンド(片づけたのにすぐ元通り)を防ぎ、長期にわたって快適な空間を維持できます。
ポイント3:定位置収納と戻す習慣を徹底する
片づけ後のキレイを保つ最大のコツは「元に戻す」ことに尽きます。すべての物に定位置(住所)を決めて収納してあるなら、使った後は必ず元の場所に戻しましょう。これを家族全員で徹底すれば、部屋が散らかりっぱなしになるのを未然に防げます。
定位置が決まっていない物は放置されがちなので、「あれの置き場が決まっていない」と気づいたら早めに居場所を作ってあげます。例えば増えた子どもの作品は専用の思い出ボックスを用意する、新しく買った掃除用具は玄関収納にフックを付けて吊す場所を作る、などです。「出したら戻す」「増えたら収納場所を確保する」というシンプルなルールを習慣化できれば、リバウンドとは無縁になります。
特に忙しいときでも、床や机の上に物を置きっぱなしにしない意識を持ちましょう。「あとで片づけよう」と思って放置すると、その上にさらに物が重なり手が付けられなくなる悪循環に陥ります。
どんなに疲れていても寝る前1分でテーブルの上だけ片づける、といった小さな習慣からでも続けることが大切です。
ポイント4:掃除しやすい環境を整える
散らかった部屋では掃除機をかけるのもひと苦労です。床に物がない状態を維持できれば、サッと掃除でき清潔さも保てます。
そこで、掃除道具をすぐ取り出せる場所に収納しておくことをおすすめします。例えばリビングでコードレス掃除機を使うなら、コンセント近くのすぐ手に取れる場所に立てかけておきます。コロコロ(粘着クリーナー)はカーペットのそばの棚に忍ばせておくなど、使う場所の近くに置くのがポイントです。
こうしておけば「ちょっとホコリが気になる」というときにサッと掃除道具を取り出して対応できます。結果的に部屋をキレイに保つ頻度が上がり、散らかりも蓄積しません。また、床置きの物を極力減らす工夫も掃除を容易にします。
収納家具は脚付きのものを選ぶと下に掃除機やロボット掃除機が入りやすく、毎日の掃除も苦になりません。
片づいた部屋+掃除のしやすさを意識して、キレイな状態を長続きさせましょう。
今日からできる小さな片づけで快適な暮らしを送りましょう
片づけは一気に完璧を目指さなくても大丈夫です。紹介した基本のルールに沿って小さなエリアから少しずつ取り組めば、忙しい人でも無理なく部屋は整います。
大切なのは「出したら戻す」「増やしすぎない」「定期的に見直す」といった習慣づけです。最初は意識が必要かもしれませんが、習慣になれば常にスッキリ片づいた空間を維持でき、気持ちにも余裕が生まれます。
家族にも協力してもらいながら、ぜひできる所から片づけを始めてみてください。片づけによって生まれる快適な暮らしは、きっと日々の生活をより豊かにしてくれることでしょう。
もし自分たちだけでは手が回らない場合は、家事代行サービスに整理整頓をお願いするのも一つの手です。プロの力を借りてでも心地よい空間を保つことで、毎日の生活の質は格段に向上します。